���t���e�ꗗSERVICE
����t
�a�@�ɂ����������A�ȉ��̋��t������܂��B
| �U�X�Έȉ��̑g���� | ����Ô���V�������t �������S���R�� |
|
| �A�w���`�U�X�̉Ƒ� | ||
| ���A�w�� | �������W�������t �������S���Q�� |
|
| �O������ҁi�V�O�`�V�S�j | ����Ô���W�������t �������S���Q�� |
��������ݏ������͑���Ô���V�������t �������S���R�� |
�I�����C�����i�m�F�����͂��܂�܂���
�@�I�����C�����i�m�F�����Q�O�Q�P�N�P�O���Q�O������{�i�^�p���J�n���܂����B�@��Ë@�ւŃ}�C�i���o�[�J�[�h�i�}�C�i�ی��j���g���ĕی��f�Â�����悤�ɂȂ�܂������A��Ë@�ւ��I�����C�����i�m�F�ɑΉ����Ă��Ȃ��ꍇ��A�ǂ݂Ƃ�@��̃g���u���Ń}�C�i���o�[�J�[�h�ɂ�鎑�i�m�F���ł��Ȃ��ꍇ������܂��B��Ë@�ւɂ�����ۂ̓}�C�i���o�[�J�[�h�����łȂ��A���茳�ɂ���ی��A���i�m�F���A���i���̂��m�点�������Ď�f���邱�Ƃ��������߂��܂��B
�������ۂ̔C�Ӌ��t
�������ۂ����̗L���ȋ��t���x�ł��B
�u�×{�t�������x�v
�U�X�Έȉ��̑g�����̎��ȕ��S���y���Ȃ�܂�
�@�������ۂɉ�������U�X�Έȉ��̑g�������Ώۂ̏��ҕ������x�ł��B��Ë@�ւ���f�����ۂɎx�����P�����̈�Ô�A�P��Ë@�ցi���@�E�O���ʁj17,500�~�����ꍇ�A�f�Ì�����R������̂Q�W���Ɏw��̌����ɗ×{�t�����Ƃ��Ďx�����܂��B
���\���s�v�Ō����ɑ��t����u�x������ʒm���v�������Ă��m�点�Ƃ��܂��B���m�F���������B
�����z�×{��̑ΏۂƂȂ����ꍇ�A���z�×{����x����c�������ȕ��S�z�����Ƃɗ×{�t�������v�Z���܂��B
���×{�t�����̎x���ΏۂɂȂ�Ȃ��ꍇ
�E�ی��f�ÂƂȂ�Ȃ����́i���@���̐H�����⍷�z�x�b�h�㓙�j
�E�J�Ђ��ʎ��̂Ȃǂ̑�O�ҍs�ׂɂ������ꍇ
�E�s����f�A���i�r���A�ی������[��������ꍇ
�E���z�×{��̐\���葱�������Ă��Ȃ�
�����������܂ނR�����͖Ɛӊ��ԂƂȂ�܂��B
�u���a�蓖���v
�a�C��P�K�Ŏd�����ł��Ȃ��Ƃ��ł����S
 �@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�g�������a�C�₯���œ��@�����Ƃ��A�ی����敪�ɉ����ʎZ���čō��P�O�O���ԁi������×{�͒ʎZ���čō��W�O���ԁj�̏��a�蓖�����x�����܂��B�O���ɂ�鍜�̐ؒf������×{�̑Ώۂł��B
�����������X�O���Ԃ͖Ɛӊ��ԂƂȂ�܂��B
���x������������ɒB�����ꍇ�A�a�C���@�͂Q�N�A�������@�ƍ�����×{�͂U�����̑Ҋ����Ԍ�A�����������܂��B
�\�����́�������
| ���a�蓖�� ���g�����̂� �i���z�j |
�ی����敪 | ���@ �i�ō��P�O�O���ԁj |
������×{ �i�ō��W�O���ԁj |
|
| ��1�� | 6,000�~ | 4,000�~ | ||
| ��1�� | 5,500�~ | 3,500�~ | ||
| ��2�� | 4,500�~ | 2,500�~ | ||
| ��3�� | 4,000�~ | 2,000�~ | ||
| ��4�� | 3,500�~ | 1,500�~ | ||
| ��5�� | 4,000�~ | 2,000�~ | ||
| ��6�� | 3,500�~ | 1,500�~ | ||
���\���ɕK�v�ȏ��ނɂ���
�@���a�蓖���A�z��ғ��@�������̐\���́A��t�̏ؖ����L�ڂ��ꂽ�u���a�蓖���E�z��ғ��@�������\�����v���o����A�܂��͈ȉ��̂V���ڂ������ނň�t���ؖ��������̂ƔF�߂���ꍇ�A�\���\�Ƃ��܂��B
�@���Ҏ����A�A���a���A�B���@�̏ꍇ�͓��@���ԁi���@�N��������ёމ@�N�����j�A������×{�̏ꍇ�͎���×{���ԁi�J���s�\���ԁj�A�C�ؖ����A�D��Ë@�֖��́A�E��Ë@�֏��ݒn�A�F��t�̏���
���\���ɕ������̏��ނ��o����ꍇ�A���ނ̊֘A�����q�ϓI�ɔF�߂��Ȃ����̂͐\���Ɏg���܂���B
����t�̏ؖ��ȊO�͔F�߂��܂���B�i�_�������t�E���n�r���e�[�V�����E�����̏ؖ��͑ΏۊO�j
���J�Ђ��ʎ��̓��̑�O�ҍs�ׂɊY������ꍇ�͎x���ΏۊO�ł��B
�u�z��ғ��@�������v
�z��҂����@�����������S
�@�g�����̉Ƒ���ی��҂ł���z��҂��a�C�₯���œ��@�����ꍇ�A�P��������2,500�~��ʎZ���čō��U�O���Ԏx�����܂��B�����ĂP���@�i�����Ë@�ւł̘A���������@�j�ɂ�5,000�~�����Z���Ďx�����܂��B
���x������������ɒB�����ꍇ�A�a�C���@�͂Q�N�A�������@�͂U�����̑Ҋ����Ԍ�A��60�����������܂��B
�\�����́�������
���\���ɕK�v�ȏ��ނɂ���
��L���a�蓖���̐\���ɕK�v�ȏ��ނƓ��l�ł��B
�u�o�Y�蓖���v
�o�Y�玙�ꎞ���Ƃ͕ʂɎx�������蓖���i�����g�������Ώہj
���o�Y�玙�ꎞ���ɂ��Ă�������
�@�����g�������o�Y�ɂ��x�Ƃ����ꍇ�A�ی����敪�ɉ����āA���a�蓖���̓��@���̓��z���o�Y���ȑO42���A�o�Y���̗����Ȍ�56�������x�Ɏx�����܂��B
���g�����Ƃ��ĉ�����180���ȓ��̕��͎x�����܂���B
�\�����́�������
�u���ۏo�Y���t���v
�o�Y�玙�ꎞ���Ƃ͕ʂɎx������鋋�t���i��ی��҂��Ώہj
���o�Y�玙�ꎞ���ɂ��Ă�������
�@��ی��҂��o�Y�i�D�P85���ȏ�̗��Y�E���Y���܂�)�����ꍇ�A�o�Y�玙�ꎞ���Ƃ͕ʂɈꎙ�ɂ��R���~���x������܂��B�o�Y�玙�ꎞ���̎x���ΏۂɂȂ�Ȃ���p�ҕی����i�r����U�����ȓ��̏o�Y���Ώۂł��B
�\�����́�������
�������ۂ̖@�苋�t
�@���Ō��߂��Ă��鋋�t�ł��B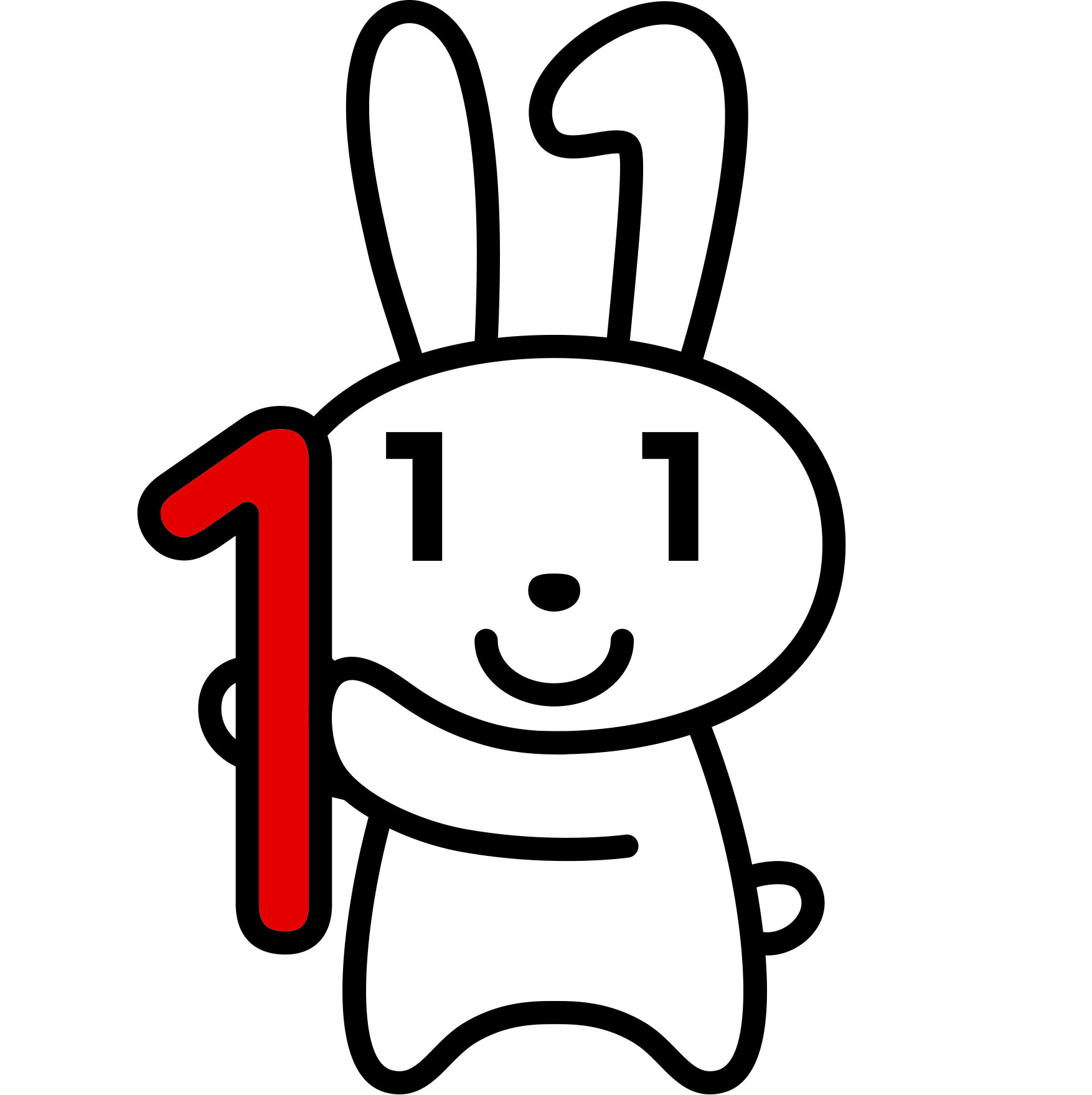 ���z�×{��̎x���\���A���x�z�K�p�F��\���A�×{��̐\���ł́A�\�����Ƀ}�C�i���o�[���L�����Ă��������܂��B�g�����ƑΏۂ̉Ƒ��̕��̃}�C�i���o�[���킩�鏑�ނƁA�͏o�҂̐g�����킩�鏑�ނ�p�ӂ��đg�������ɒ��Ă��������B�ڂ�����������
���z�×{��̎x���\���A���x�z�K�p�F��\���A�×{��̐\���ł́A�\�����Ƀ}�C�i���o�[���L�����Ă��������܂��B�g�����ƑΏۂ̉Ƒ��̕��̃}�C�i���o�[���킩�鏑�ނƁA�͏o�҂̐g�����킩�鏑�ނ�p�ӂ��đg�������ɒ��Ă��������B�ڂ������������g�����ȊO�̕����葱�����s���ꍇ�́A�g�������M�̈ϔC�K�v�ł���������
�u���z�×{��v
�@��Ë@�ւŎx������Ô�̎��ȕ��S�z�����z�ɂȂ����Ƃ��́A���z�i���ȕ��S���x�z�j�����z�����ۂ���x�����܂��B��������z�×{��Ƃ����܂��B�i�A���A�ی��f�ÂɂȂ�Ȃ����@���̐H�����⍷�z�x�b�h��͍��z�×{��̑ΏۊO�ł��B�j
�@�P�����i�P�����疖���j�ɂP��Ë@�ցi���@�E�O���ʁj�Ɏx���������z�i�Q���܂��͂R���j�����L�̕\�̌��x�z�����ꍇ�A��f��R�������߂ǂɁu���z�×{��x���\�����v���Y�����тɑ��t���܂��B�\���̍ۂ́u���z�×{��x���\�����v�Ɨ̎����E���z�×{��\���葱���ȑf���\�����i��1�j�������̑g���ɒ�o���������ƁA���炩���ߓo�^���������������ɐU�荞�݂܂��B
�@�܂��A��Ë@�ւł̎x���������ȕ��S�z�܂łɂ������Ƃ��́A���x�z�K�p�F��i��2�j���K�v�ƂȂ�܂��̂ŁA���O�Ɍ�t�\�����s���Ă��������B
���P�@���z�×{��̎x���\���ȑf���Ƃ�
�@���ۖ@�{�s�K���̈ꕔ�����ɂ��A�\���葱�����ȑf�����邱�Ƃ��\�ɂȂ�܂����B����ɔ������z�×{��̐\�������u���z�×{��\���葱���ȑf���\�����v����x��o�����������ƂŁA�ȍ~�̐\���葱���͕s�v�ƂȂ�܂��B
�E�ȑf���̎葱���ȍ~�̍��z�×{��́A�U�����̌����ɂ����肷��u�x������ʒm�v�����m�F���������B
�E��Ë@�ւ̐����x���A���������̉�����Ă��Ȃ��ꍇ���͎x�����x���ꍇ������܂��B
�E�\���ȑf���葱�������Ă��Ȃ��ꍇ�A�]���ʂ育����ɍ��z�×{��x���\�����������肵�܂��̂ŁA�̎�����Y���ď����̑g�������Ő\���葱�����s���Ă��������B
�E�����敪�̕ύX���ɂ��x���z�ɕύX���������ꍇ�A��Ë@�ււ̖������������o�����ꍇ�͎x���ς݂̍��z�×{���Ԋ҂��������ꍇ������܂��B
�E�ȑf���̎葱����ɁA���т̈ٓ����őg�������ς�����ꍇ�́A�ēx�x���\���ȑf���̎葱�����K�v�ł��B
���Q�@���x�z�K�p�F��Ƃ�
�@���@�E�ʉ@�ɌW���Ë@�ււ̎x�����ɂ��āA���O�Ɂu���x�z�K�p�F��v�������̑g���ɐ\�����A��Ë@�ւ̑����ɒ�o����ƁA���L�\�̌��x�z�܂ł̎x�����ōς݂܂��B���x�z�F��͐\�����̂P������K�p����܂��B����k�������s�͏o���܂���̂ŁA���߂̐\�������肢���܂��B
70�Ζ����̏ꍇ
| �����敪 �i�����������������j |
���ȕ��S���x�z �y�@�z���͂S��ڈȍ~�̌��x�z |
|---|---|
| �敪�A �i901���~���j |
252,600�~�{�i���|842,000�~�j�~�P�� �y140,100�~�z |
| �敪�C �i600���~��~901���~�ȉ��j |
167,400�~�{�i���|558,000�~�j�~�P�� �y93,000�~�z |
| �敪�E �i210���~��~600���~�ȉ��j |
80,100�~�{�i���|267,000�~�j�~�P�� �y44,400�~�z |
| �敪�G �i210���~�ȉ��j |
57,600�~ �y44,400�~�z |
| �敪�I �i�Z���Ŕ�ېŐ��сj |
35,400�~ �y24,600�~�z |
70�Έȏ�̏ꍇ
| �����敪 | ���ь��x�z �y�@�z���͂S��ڈȍ~�̌��x�z |
|
|---|---|---|
| �O�� �i�l���Ɓj |
||
| ������݇V �i�ېŏ���690���~�ȏ�j |
252,600�~�{�i���|842,000�~�j�~�P�� �y140,100�~�z |
|
| ������݇U �i�ېŏ���380���~�ȏ�j |
167,400�~�{�i���|558,000�~�j�~�P�� �y93,000�~�z |
|
| ������݇T �i�ېŏ���145���~�ȏ�j |
80,100�~�{�i���|267,000�~�j�~�P�� �y44,400�~�z |
|
| ��� �i�ېŏ���145���~�����j |
18,000�~ ���N�ԏ��144,000�~ |
57,600�~ �y44,400�~�z |
| �Ꮚ���҇U �i�Z���Ŕ�ېŐ��сj |
8,000�~ | 24,600�~ |
| �Ꮚ���҇T �i�Z���Ŕ�ېŐ��сm���������ȉ��n�j |
15,000�~ | |
���@���̐H������ѐ����×{�̔�p�ɂ���
�a�@�E�f�Ï��ɓ��@�����Ƃ��̐H������̔�p�ɂ��ẮA���Ô�Ƃ͕ʂɑ����ŕW�����S�z���x�����A�c��̔�p�͓��@���H���×{��܂��͓��@�������×{��Ƃ��Ē������ۂ����S���܂��B
�������×{��ɂ��ẮA�×{�a���ɓ��@����U�T�Έȏ�̕����Ώۂł��B
���������ۂ̍��z�×{���×{�t�������x�̑Ώۂɂ͂Ȃ�܂���B
���@���H���×{��̕W�����S�z�i�P�H�ɂ��j
�E���@���ĐH���×{�����ꍇ�̂P�H�̕W�����S�z�͉��\�̒ʂ�ł��B���ߘa�V�N�S������W�����S�z���ς��܂����B
| ��ʁi�V�O�Ζ����j | �V�O�Έȏ� | �敪 | �W�����S�z�i�P�H�j | |
|---|---|---|---|---|
| �ߘa�V�N�R���܂� | �ߘa�V�N�S������ | |||
| ��� | �@�j��� | ���L�ȊO | �S�X�O�~ | �T�P�O�~ |
| �w���a���ҁE�����������莾�a������ | �Q�W�O�~ | �R�O�O�~ | ||
| �Ꮚ���� | �A�j�Z���Ŕ�ېŐ��� �i�Ꮚ���҇U�j |
�@�ߋ��P�N�Ԃ̓��@�������X�O���ȓ� | �Q�R�O�~ | �Q�S�O�~ |
| �A�ߋ��P�N�Ԃ̓��@�������X�O�����i���P�j | �P�W�O�~ | �P�X�O�~ | ||
| �Y���Ȃ� | �B�j�Z���Ŕ�ېŐ��сi�Ꮚ���҇T�j | �P�P�O�~ | �P�P�O�~ | |
���@�������×{��̕W�����S�z�i�P�H�E�P���ɂ��j
�E�×{�a���ɓ��@����U�T�Έȏ�̕����Ώۂł��B�H���ƌ��M����i���Z��j�ɂ��Ă̕W�����S�z�i�H���{���Z��j�͉��\�̒ʂ�ł��B���ߘa�V�N�S������W�����S�z���ς��܂����B
| �×{�a���ɓ��@���� �U�T�Έȏ�̔�ی��� |
�W�����S�z | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| �H���i�P�H�j | ���Z�� �i�P���j |
||||
| �ߘa�V�N�R���܂� | �ߘa�V�N�S������ | ||||
| ��� | �@���L�̂�����ɂ��Y�����Ȃ��� | ���@�����×{�i�T�j���Z�肷���Ë@�� | �S�X�O�~ | �T�P�O�~ | �R�V�O�~ |
| ���@�����×{�i�U�j���Z�肷���Ë@�� | �S�T�O�~ | �S�V�O�~ | |||
| �A�d�ĂȏǏ�܂��͏W���I���Â�v����ғ� | ���@�����×{�i�T�j���Z�肷���Ë@�� | �S�X�O�~ | �T�P�O�~ | �R�V�O�~ | |
| ���@�����×{�i�U�j���Z�肷���Ë@�� | �S�T�O�~ | �S�V�O�~ | |||
| �B�w���a���� | �Q�W�O�~ | �R�O�O�~ | �O�~ | ||
| �Ꮚ���U | �C�Ꮚ���U�i�D�A�E�ɊY�����Ȃ��ҁj | �Q�R�O�~ | �Q�S�O�~ | �R�V�O�~ | |
| �D�Ꮚ���U�i�d�ĂȏǏ�܂��͏W���I���Â�v����ғ��j | �@�ߋ��P�N�Ԃ̓��@�������X�O���ȓ� | �Q�R�O�~ | �Q�S�O�~ | �R�V�O�~ | |
| �A�ߋ��P�N�Ԃ̓��@�������X�O�����i���P�j | �P�W�O�~ | �P�X�O�~ | |||
| �E�Ꮚ���҇U�i�w���a���ҁj | �@�ߋ��P�N�Ԃ̓��@�������X�O���ȓ� | �Q�R�O�~ | �Q�S�O�~ | �O�~ | |
| �A�ߋ��P�N�Ԃ̓��@�������X�O�����i���P�j | �P�W�O�~ | �P�X�O�~ | |||
| �Ꮚ���T | �F�Ꮚ���T�i�G�A�H�ɊY�����Ȃ��ҁj | �P�S�O�~ | �P�S�O�~ | �R�V�O�~ | |
| �G�Ꮚ���T�i�d�ĂȏǏ�܂��͏W���I���Â�v����ғ��j | �P�P�O�~ | �P�P�O�~ | �R�V�O�~ | ||
| �H�Ꮚ���T�i�w���a���ҁj | �P�P�O�~ | �P�P�O�~ | �O�~ | ||
���P�j�ߋ��P�N�Ԃ̓��@�������X�O�������ꍇ�A�\�ɋL�ڂ��ꂽ�W�����S�z�ɂ���ɂ́u���x�z�K�p�E�W�����S�z���z�F��v���K�v�ł��B�����̑g���Ő\�������Ă��������B�\�����x�ꂽ���ɂ��W�����S�z�ȏ���x�������ꍇ�́A�\���ɂ�荷�z�̎x�����邱�Ƃ��ł��܂��B
�u�o�Y�玙�ꎞ���v

�@��ی��҂��o�Y�����Ƃ��A�ꎙ�ɂ��T�O���~�����t����܂��B�o�Y�玙�ꎞ���ɂ͂R�̐��x������A�����ꂩ�̕��@�ŋ��t������邱�Ƃ��ł��܂��B
�@���ڎx�����x
�@�o�Y�玙�ꎞ��������Ë@�ւɒ��ڐU�荞�݂܂��B�o�Y�̍ۂ̑������S���y������郁���b�g������܂��B���x�𗘗p����ɂ͈�Ë@�ւ\���o�āA���ӏ��������킷�K�v������܂��B��Ë@�ւ̐����z���T�O���~�����̏ꍇ�͍��z���ی��҂ɂ��x�����������܂��B
�A���㗝���x
�@���ڎx�����x�Ɠ������A�o�Y�玙�ꎞ��������Ë@�ւɒ��ڐU�荞�݂܂��B���x�𗘗p����ɂ́A�������ۂ��o�Y�玙�ꎞ���x���\�����i���㗝�p�j���o���Ă��������B��Ë@�ւ̐����z���T�O���~�����̏ꍇ�͍��z���ی��҂ɂ��x�����������܂��B
�B�ʏ�̎x���\��
�@��Ë@�ւɏo�Y��p���x��������A��q�蒠�̎ʂ��A�o�Y��p�̗̎��E������Y�t���āu�o�Y�玙�ꎞ���x���\�����v���o���Ă��������܂��B�x�����ɂT�O���~���o�^���������ɐU�荞�܂�܂��B
�@�o�Y���O�U�����ȓ��ɔ�p�ҕی��i�����ۂ⌒�ۑg�����j���璷�����ۂɉ����������̂����A�{�l�i��ی��ҁj�Ƃ��Ď��i�r�����܂łP�N�ȏ�p�����Ĕ�p�ҕی��ɉ������Ă������́A��p�ҕی�����o�Y�玙�ꎞ������邱�Ƃ��ł��܂��B���̏ꍇ�A�d�����t������邽�ߒ������ۂ���͋��t����܂���̂ŁA�ȑO�������Ă�����p�ҕی��ɐ\�����Ă��������܂��B���ڎx�����x�̗��p����Ë@�ւ\���o��ۂɂ́A�K���u�ȑO�ɉ������Ă�����p�ҕی��ŏo�Y�玙�ꎞ�������v�|���A�����Đ\���o�ĉ������B
���Ք�
�@�g���������S�����Ƃ���70,000�~�A�Ƒ���ی��҂����S�����Ƃ���50,000�~���u���̑��Ղ��s�����́i�r��j�v�ɑ��Ďx������܂��B�\���葱�����s���ۂ̐����҂́A�r��ł��邱�Ƃ��K�v�ł��B
�\�����́�������
�×{��
�́A�×{��̎x���ΏۂƂȂ�\��������܂��B�ڂ����͑g���ւ��₢���킹�̏�A�Y�t������p�ӂ��Đ\�����Ă��������B
- �ی���Ë@�ւ���f�����ۂɁA��ނȂ����R�łP�O�����̐f�Ô���x�������ꍇ
- ���×p����A�����㎋���̎��×p�ዾ����������ꍇ
- �͂�A���イ�A�}�b�T�[�W������
- �C�O�ň�҂ɂ���������
�@�Q�O�P�X�N�S�����A����܁E�͂�E���イ�E�}�b�T�[�W�̎�̈ϔC�������x���n�܂��Ă��܂��B
�����̑��A���z�×{��ݕt���x��o�Y����ݕt���x������܂��B
����
�����͂Q�N�Ԃł��B
�o�i�[�X�y�[�X
���쌧���ݍ������N�ی��g��
��390-0864
���쌧���{�s�{���{���P�|�Q
���J���
TEL 0263-39-7080
FAX 0263-39-7082